みなさん、家を購入する際の「引き渡し日」って、具体的に何をする日か知っていますか?
不動産購入において、引き渡し日というのは契約日と並ぶ、最も重要なイベントの一つと言えます。
ここでは、引き渡し日の重要性や、契約日から引き渡し日までの期間に準備しなければならないこと。
さらに、私たちが体験した引き渡し日の実際の流れなどを詳しく説明していきます。
この記事を書いているのは、DIYリフォームをしながら「好きな時に、好きな場所で、好きなことをしながら生活をする」という目標に向かって日々DIYをしている「トリノベ」管理人の【トリさん】です!よろしくお願いします。
引き渡し日とは
引き渡し日はというのは、「不動産の売買契約に基づき、売主から買主へ物件の所有権が移る日」のことを言います。
家を買う約束をする日が契約日で、実際に建物の鍵を受けとり「これからここが私の家だ!」と言える日が引き渡し日です。
この日を境に、その家は完全に自分のものになり、リフォーム工事や引っ越しなど、何をするにも自由になるわけです。
ちなみに、引き渡し日には物件売買費用の残金も売主へ支払います。
つまり簡単に言うと、「お金を払って、鍵(家)を受け取る日」が引き渡し日です。
引き渡しをすると何が起こる?
物件が自分たちのものになる
引き渡し日当日、司法書士(登記の手続きを行ってくれる専門家)に所有権移転の手続きを進めてもらい、登記簿の情報が変更することで、その物件はようやく自分たちの持ち物になります。
自分たちの持ち物になるということは、リフォーム工事や引っ越しなど、何をするにも自由になります。
鍵の管理も自分たちで行うため、当然出入りも自由です。
裏を返せば、引き渡し前は鍵をもっていないため、契約を結んだ後であっても自由に出入りをすることはできません。
様々な費用が発生する
- 固定資産税
- 不動産取得税
建物を所有すると、様々な費用が発生します。
一つ目は固定資産税です。
取得した不動産の土地と建物の両方に課税され、毎年支払いが必要になる税金です。
ちなみに、年度の途中だと月割りの計算になるため、引き渡し日をいつにするかで金額に影響が出てきます。
二つ目は、不動産取得税です。
固定資産税同様、取得した不動産の土地と建物両方に課税されますが、こちらは不動産取得時に一度だけ支払う税金です。
登記が完了すると請求書が送られてくるのですが、請求所が届くまで4~6か月かかるのが一般的のようです。
司法書士の先生にも、忘れたころに請求が来るから、お金の準備を忘れないでと忠告をうけました。
引き渡し日はいつにするのがベスト?
契約を行ったときに、「引き渡し日をいつにするかどうか」確認をされます。
引き渡しをした時点で、家は自分たちの所有物になる代わりに、そこから税金(固定資産税)が発生してきます。
つまり、引き渡し後、いつ引っ越しをするのか?リフォーム工事を行う場合、いつから工事を開始したいのか?といった、その後の予定に合わせて引き渡し日を設定したほうが良いことになります。
我が家の場合、すぐに引っ越しをしたい訳ではなかったため(保育園が決まっておらず、引っ越しをすることができなかった)引き渡し日をなるべく先に伸ばしてくださいとお願いしました。
保育園問題についてはこちら↓↓↓の記事ににまとめてあります。ぜひ参考にしてみてください。
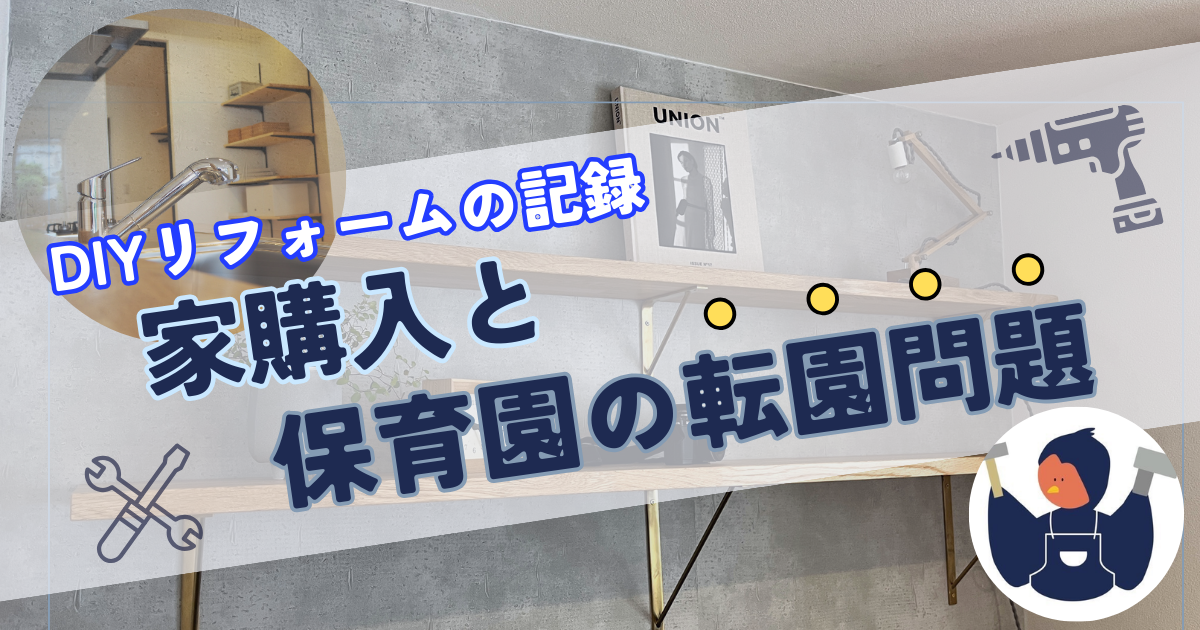
結果的に、契約日が2021年1月23日(土)で引き渡し日が4月27日(火)ということに決めました。
ちなみに、契約日は土曜だったのですが、引き渡し日は平日の午前中でお願いしますと言われました。
理由としては、お金のやり取りをするため銀行が開いてる日じゃないとまずいからということです。詳しくは後程・・・
引き渡し日に向けた準備
引き渡し日までにやるべきこと
契約日から引き渡し日までにやるべきことは以下の通りです。
- 契約内容の最終チェック
- 資金計画の最終確認
- 必要書類の準備
- 工事などの準備
- 保険の加入
- 転園・転校手続き
- 引っ越し準備
契約内容の最終チェック
引き渡し日の流れは、不動産会社と打ち合わせをして決めてください。引き渡しの場所は、不動産会社や銀行の打ち合わせスペースなどが考えられます。
また、引き渡し前に物件を再度確認し、約束された条件や修繕が適切に行われていることもチェックしましょう。
契約時に売主様の負担で行うことになっている内容は、引き渡しまでに完了しているか必ず確認をしてください。
資金計画の最終確認
住宅ローンを利用場合、支払いがスムーズに開始されるように、金融機関との連絡を密に取りましょう。
引き渡し後のリフォーム代金や、固定資産税、不動産取得税の支払いなどの資金計画もしっかり行い、予期せぬ出費に備え、余裕を持った計画を立てください。
必要書類の準備
所有権移転に必要なすべての書類が揃っていることを確認し、引き渡し日に備えます。
印鑑証明や、身分証明書、通帳など引き渡しに必要な書類は事前に準備し、当日忘れることがないように、事前に確認をしておきましょう。
リフォーム工事の準備
事前に現地調査をお願いして見積りしてもらっておくと、引き渡し後すぐに工事に取り掛かることができます。
風呂やトイレ、キッチンなどの住宅設備機器をショールームに見に行く場合、早めに見学に行って仕様を決定しておきましょう。
補助金や、ポイント申請などがある場合、期限や期間の確認も忘れずに。
工事に伴い購入した物件に住めない場合、一時的な住居(仮住まい)が必要です。賃貸住宅やホテルなど、期間に応じて準備がしてください。
保険の加入
引き渡し日の前に、必要な保険には加入しておきましょう。
特に火災保険は、引っ越し前であっても忘れずに加入してください。
引っ越し前に火事が起きて、家がなくなってしまい、支払いだけが残る・・・
もしものためにも、必要な保険には加入しておくことをおすすめします。
転園・転校手続き
特に、保育園の転園は、待機児童の問題もあるため、必要書類を集め、早めに手続きを開始することをおすすめします。
ちなみに、我が家にとっても娘の保育園問題が、引っ越し前の一番のネックでした。
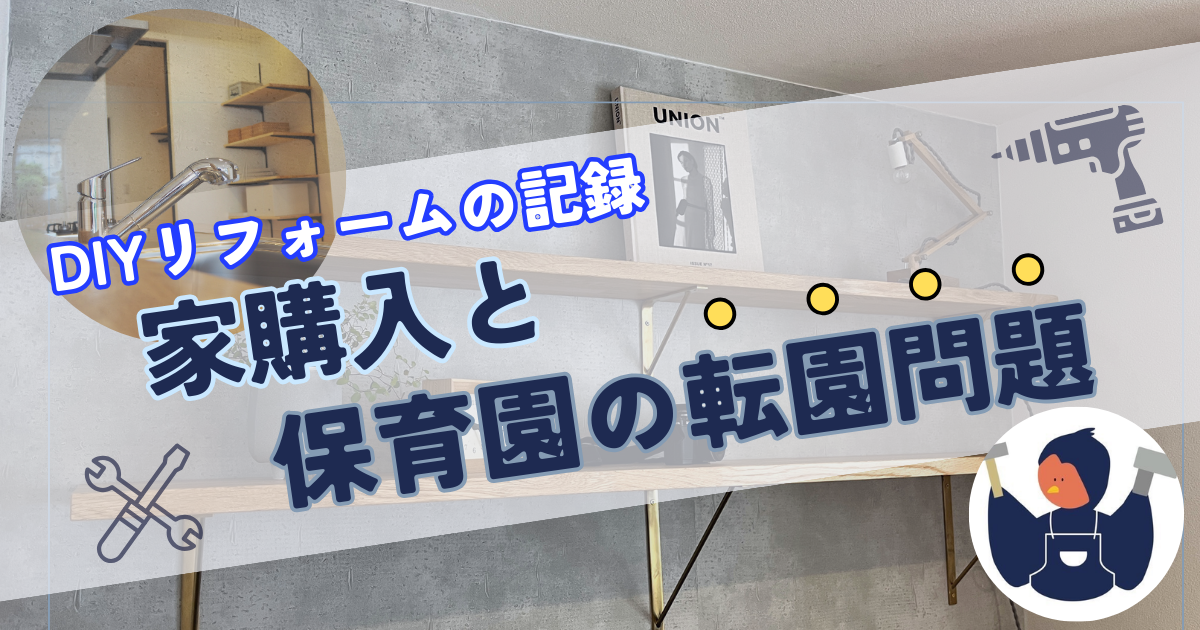
3. 引っ越し準備
引き渡し後、引っ越しの予定が決まっている場合、引き渡し日に合わせて、信頼できる引越し業者を早めに予約しておきましょう。
3月末などの繁忙期は、すぐに予約が埋まってしまう可能性があるため、早めに予約をすることをお勧めします。
引っ越し業社を選ぶ際は、必ず複数の引越し業者から見積りをしてもらいましょう。
一括サイトなどを利用するのもありだと思います。
引き渡し日にやる事
引き渡し当日の流れは
不動産会社にて書類記入→残代金決済→各種登記手続き→鍵の引き渡し
という流れになることが一般的です。
持ち物:印鑑、通帳、身分証明書は必須です。
書類記入と確認:不動産会社での最終書類の記入と確認を行います。
残金の決済:銀行での残金支払いを行い、その場で売主に支払います。
登記手続き:司法書士が登記簿の変更を行い、物件が買主名義になることを確認します。
鍵の受け取り:全ての手続きが終わった後、不動産会社から物件の鍵を受け取ります。
引き渡し日までにしっかりと準備を進めることで、新居での生活をスムーズに始めることができます。
我が家の引き渡し日 当日の様子
最後に、我が家の引き渡し日当日の流れをまとめていきます。
不動産屋に集合
2021年4月27日(火)朝9時に不動産屋に集合しました。
すでに売主さんも来ており軽く雑談しすぐに書類に記入を始めます。
書いた書類は次の通りです。
- 大量の銀行の振り込み用紙
- 登記簿に関する書類
- 鍵を受け取るための書類
特に、銀行の振り込み用紙は大量で、全部で8枚ほど記入しました。(内容は忘れてしまいましたが、項目を分けて記入しました。)
約1時間かけて、全ての書類に署名と捺印を行い、その後色々な説明を受け、最後に鍵を受け取りひと段落。
銀行へ移動
鍵の引き渡しまで完了したら、残金を払うために銀行へ移動します。
今回は不動産屋近くのみずほ銀行の支店まで、全員で歩いて向かいました。
到着すると、平日の昼間にも関わらず、銀行内は激混みです。整理券を受け取り並びながら待ちます。
銀行の手続きに1時間ほどかかるとのことで、その間に司法書士の先生や不動産担当者に色々と質問して過ごしました。
入金が行われたことをお互いに確認して、引き渡しの手続きが完了となります。
ちなみに、確認作業は通帳を見るというアナログな方法で行われました。
引き渡し完了
鍵を受け取ったあと、さっそく家に向かい記念撮影を行いました。
念願の「何をしても良い家」が手に入った瞬間でした。
まとめ
引き渡し日に向けてしっかりと準備を進めることで、当日の手続きをスムーズに行うことができるだけなく、新居での生活を安心して迎えられるようになります。
皆さんにとって、引き渡し日という新しいスタートが、素晴らしい日になることを心から応援しています。

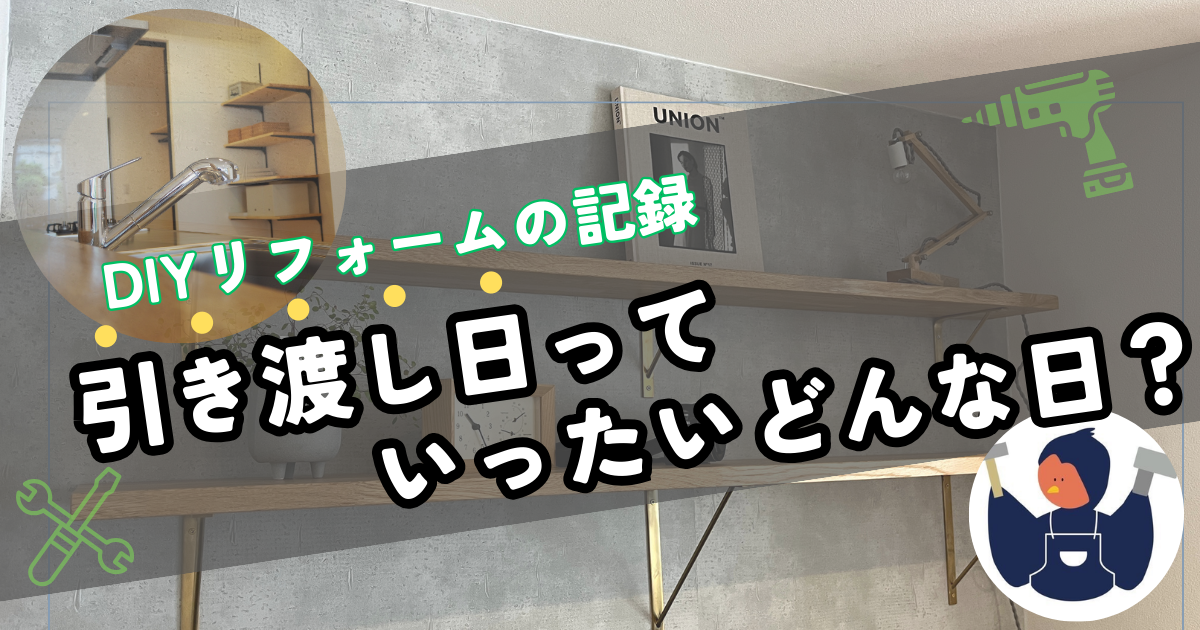

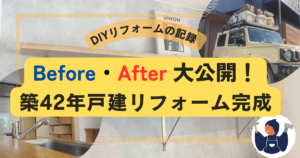







コメント